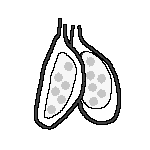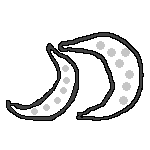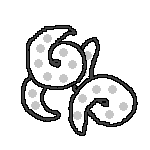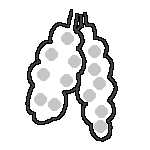サンショウウオのたまご 晩冬から春先にかけて、サンショウウオは産卵の季節を迎えます。 かたち 卵のうはサンショウウオの種類ごとに決まったかたちをしているので、サンショウウオの種類を特定する大きな手がかりになります。山渓ハンディ図鑑9「日本のカエル+サンショウウオ類」では、卵のう型を次の4つに区分しています。 アケビ型
バナナ型
コイル型
ヤマブドウ型
ちなみに、オオサンショウウオは上のどれでもなく、数珠のようにつながったひも型の卵のうを産みます。 一房の卵のうの中に、いくつくらいの卵が入っているかはサンショウウオの種類だけでなく、産卵の時期や産卵場所の標高などによっても異なります。図鑑によると、大雑把に言って流水性で10〜20個、止水性で20〜100個くらい。オオサンショウウオなどは、1度に500個ほども産むそうです。 また、よくサンショウウオの卵をアカハライモリの卵と勘違いされることがありますが、アカハライモリは、上のどのタイプでもなく、直径5mmほど(卵径およそ2mm)の卵を一粒ずつ水草や水中の枯葉などに産み付けます。 大きく膨らむ仕組み サンショウウオの卵のうは、それを産む親よりもずっと大きいです。クロサンショウウオの卵のうなど、握りこぶしほどあるものも。小さなサンショウウオが、どうしてあんなに大きな卵のうを産めるの!?実は産み出されてから、外側を包んでいる寒天質が水を吸って大きく膨らむのです。 ヒダサンショウウオの卵のう
|
|
止水性のクロサンショウウオは、渓流ではなく沼地のような水の流れのない場所(止水)に卵を産みます。卵のうの外見もヒダサンショウウオのものとは全然違います。 |
なぜでしょうか?それはヒダサンショウウオが渓流に卵を産む流水性のサンショウウオであることに関係があるようです。
流水性の卵はなぜ大きいか
ヒダサンショウウオの幼生は孵化しても、すぐには卵のうから外に出ません。なぜなら、外は流れのある水。流されない体力を備えるまで育つ必要があるからです。それで、餌を摂らなくてもしばらくは卵のうの中で成長できるように、栄養のたくさん詰まった大きい卵で生まれてくるのだそうです。
クロサンショウウオの場合は、孵化した時点で卵のうから外に飛び出します。飛び出した先は流れのない止水ですから、体力がなくても流されてしまうことはありません。流水性のヒダサンショウウオにとっては、卵のうの中が、止水と同じ環境を持っているといえます。
もうひとつの理由として、沼地などの濁った水の中には、サンショウウオの餌になる生物がたくさんすんでいますが、水のキレイな渓流ではそうはいきません。そんな場所にたくさんの子供を産んでは、共倒れになってしまいます。ですから、流水性のサンショウウオは量より質。大きくて丈夫な子供を少しだけ産むわけです。
一方の止水性サンショウウオは質より量とばかりに、たくさんの卵を産みます。孵化したばかりは小さくても、まわりにたくさんある餌をどんどん食べて、たちまち大きくなるのですから。
参考文献・・・ヒダサンショウウオの発生段階図表(秋田 喜憲)
| ←戻る |
|
トップページ > サンショウウオとは > 生活史 > サンショウウオのたまご
 |
URL : http://xto.be/ | ご質問等ありましたら掲示板にお願いします。 ※完全リンクフリーです。ご自由にどうぞ。 |