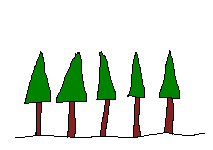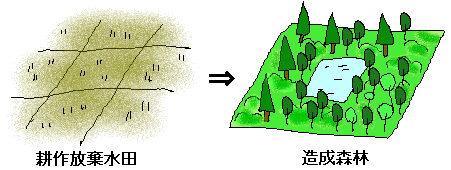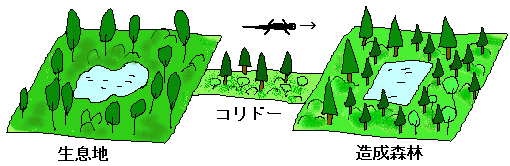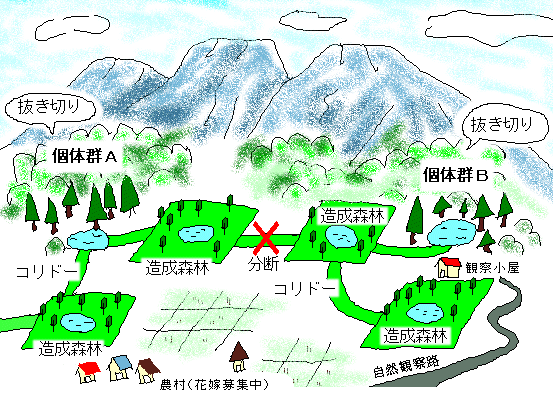サンショウウオのための森林作り
サンショウウオのようにひっそりと隠れ住む生物は、世間の関心を集めにくく、保護のための十分な配慮がなされていない現状にあります。
逆に、どう配慮してよいか良くわからないという面もあろうかと思います。
そこで今回、止水性の小型サンショウウオの保護に視点を置いた森林作りについてまとめてみました。
既存の生息地の整備について
もともと人の手があまり入っていない原生的な森林は、そのまま自然の流れにまかせるべきですが、一旦人間が手をかけた森林は、その後も適切な面倒をみていかなければ健全な状態を維持できません。意外かもしれませんが、森林作りにおいて初めにやるべきことは木を切ることです。
適切な伐採方法
サンショウウオはうっそうとした薄暗い森林を好むことから、長い年月をかけて大木を育てていくことが必要です。かといって、木を切らないで放っておけばどうでしょう。もやしのようなひょろひょろの木ばかりが育ち、自然災害に弱い貧弱な森林になってしまいます。
そこで、適切な方法で木を切り、健全な成長の手助けをしていくことが重要になります。
|
木を切るには、いっせいに切る方法と、抜き切りをする方法があります。
木をいっせいに切ると作業が簡単で経費的にも有利ですが、次の木が育つまで、林床は日ざらし・雨ざらしとなってしまい、もはやそこでサンショウウオは生きていけません。
|

皆伐イメージ
|
よって、サンショウウオのための森林作りは、抜き切りを行います。
抜き切りをした後には、新しく木の苗を植えるも良し、自然に新しい木が生えるのを待って、原生的な森林に近づけていくも良し(サンショウウオは森林を構成する木の種類には特にこだわらない。逆に言うと、もともとサンショウウオが棲む環境にはその環境に適した木しか育たない)。
|
抜き切りは面倒で、経費的にも効率的にも良くありませんが、切り残された木が風や大雪などから幼木をガードする役目をし、また、切り残された木自身も周りにライバルが減ったことで日光や養分を余計に吸収できるなど、木の成長にとって大きなメリットがあります。
以上のように、「抜き切りをして新しい木を育て、また抜き切りをする」という方法を繰り返せば、そこに棲むサンショウウオへの影響を最小限に抑えつつ、健全な森林を育てていくことが可能なのです。
|
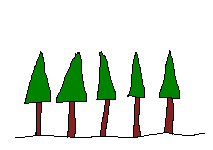
択伐イメージ
|
新しい生息地の整備について
次に、新しくサンショウウオの生息地を作り出すための森林整備の方法について。
クロサンショウウオをはじめ止水性の小型サンショウウオは、新しい水場に比較的すんなりとなじみ、そこを新たな繁殖場所とする性質があるため、産卵のための水場と生息のための森林をセットで整備することで、新たな生息環境を創り出すことが可能と考えられます。
耕作放棄水田をサンショウウオの楽園に!
私は耕作放棄水田の利用に着目しました。
耕作放棄水田とは、減反政策や労働力不足等が原因で米作りをやめてしまった田んぼのこと。特に山間地の里山に多く分布し、放っておくと荒地化して土砂崩れや地すべり被害をもたらすなど、社会問題のひとつになっています。
そこで、それら里山に存在する耕作放棄水田の一部をサンショウウオ繁殖用のため池として整備し、周囲一体を土壌改良等施して木を植えることで、新たなサンショウウオの生息環境を創出し、ついでに荒地化問題を解決するというアイデアを提案します。
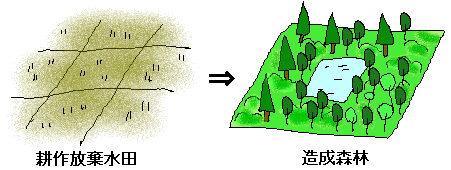
ここで、「人間の手で作り出した環境はその範囲内だけで管理し、もともとの自然環境に極力影響を与えないようにすべき」との考えから、造成森林の周りでは定期的に草刈りを行って日当たりを良くし、サンショウウオが外部に拡散しないよう配慮します。それに加えて
─ここがポイントですが─ 遊歩道等を整備して自然観察やレクリエーションの場として広く市民に開放します。
すなわち、私が提案したいサンショウウオのための森林作りは、サンショウウオのためだけでなく、市民の保健休養の場として有効利用する里山のいこいの空間作りでもあるのです。(話がデカくなってきた(汗))
移動通路(コリドー)の整備
さて、サンショウウオのために新しい森林を創っても、そこにサンショウウオがやってこなければ意味がありません。もっとも簡単なのは元いた場所から移植する方法ですが、生息条件が合わなければ定着は望めません(サンショウウオの生息条件の解明は未だ不十分)。
そこで、元々の生息地と新しく作った森林を帯状の森林帯で結んでサンショウウオ移住用の通路として整備し、自然の成り行きに任せることにします。このように生息環境同士を結ぶ森林帯を、専門用語でコリドー(回廊)といいます。
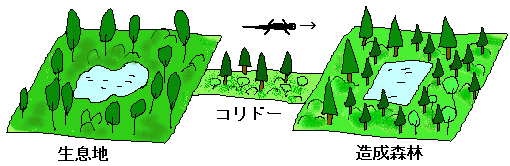
サンショウウオ用のコリドーは、変態を終えて上陸した幼体の誘導経路とする目的で設置し、繁殖池を基点として長さ300メートル以下のごく小規模なものとします(距離を稼ぐには生息地→コリドー→造成森林→コリドー→造成森林→コリドー・・・と連続配置する)。
コリドーの幅は、一般には対象生物の普段の生活直径程度を設けるとされていますが、サンショウウオの場合、30メートルもあれば十分でしょう。
さらに、サンショウウオ幼体は変態して上陸後、暗いほうへ暗いほうへと移動する性質があることから、確実にコリドー内を移動させるためには、その内部だけを暗くしておく必要があります。そこでコリドー周囲は造成森林の周囲と同様に、空を覆うような木が育たないよう配慮します。
なお、サンショウウオは地域ごとの遺伝分化が大きいため、個々の個体群を遺伝子レベルで保護する観点から、異なる個体群同士をコリドーによってつなげないことに注意を要します。
まとめ
以上のサンショウウオのための森林作りについてまとめると、下図のようになります。
「サンショウウオのための森林作り イメージ図」
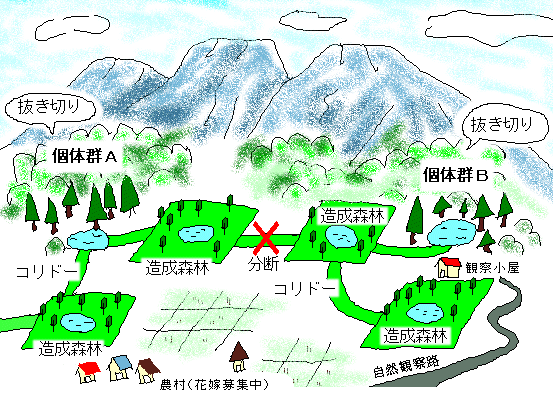
さて、ここで現実の大きな壁に直面します。
森林を育てるには、何十年にも渡る途方もない時間が必要であり、しかも、このような大規模なプロジェクトとなると、土地所有者個人はもとより、地域のボランティア活動などだけでは、どうしても限界があるのです。
何かよい解決策はないでしょうか。
自然再生推進法について
過去の大規模な公共事業や開発行為などで失われてしまった自然環境を取り戻すことを狙いに、自然再生推進法が平成14年1月1日より施行されています。
「自然を取り戻す。」
なんとも口に甘く耳に快い。
ところが、たくさんの問題点があるとして、各方面から懸念の声が上がりました。
-
公共事業で自然を破壊し、別の公共事業で自然を再生するというばかげた矛盾が生じかねない。
⇒ある干潟を埋め立てる。そのかわり、別の場所に人工干潟を作ってお茶を濁す。
-
公共事業を増やすための口実になりかねない。
⇒公共事業で自然を壊し、また公共事業で自然を再生することをくりかえせば、飯の種に困らない。
-
今ある自然をいかに守るか考えることが先決ではないか。
⇒自然破壊に歯止めをかけずして、再生再生といっても意味がない。
このように問題点は多いものの、出来てしまったからには有効に活用するのが利口です!
この法律に基づく自然再生事業によって、サンショウウオのための森林作りを進めることを検討してみたいと思います。
自然再生事業を立ち上げよう!
自然再生推進法の目玉の一つに、行政だけでなく、地域住民や民間非営利団体(NPO)が事業の計画段階から参加できる点が挙げられます。つまり、その気になれば一市民が音頭をとって、自然再生事業を立ち上げることが可能ということ。おおっ!(・∀・) イケそうだ!
以下に事業立ち上げの流れを説明します。
まずは、発案者自ら、次のメンバーからなる自然再生協議会を作ります。
・・・いきなり挫折。
個人がコレだけのメンバーをそろえるのは生半可なことではないでしょう。せっかく地域住民が参加できるのが売りの事業なのに、出だしからハードルが高すぎる・・・。
協議会を作ることが出来たなら、県などの助言を受けながら全体構想、計画案の作成・公表を経て、自然再生事業の実施にこぎつけることが出来ます!
皆さん、ガンバッテください(超無責任)。
参考文献・・・「森林における野生動物の保護管理」(日本林業調査会)
「耕作放棄水田の実態と対策」(中川昭一郎)
「里山の自然を守る」(石井実・植田邦彦・重松敏則)
|
既に絶版となっている金井郁夫氏の著書「自然の記録シリ−ズ トウキョウサンショウウオ 生活の神秘をさぐる」(誠文堂新光)には、筆者がサンショウウオの飼育、調査、研究などに没頭していく様子や、サンショウウオ保護への取り組みの様子が描かれています。
この本が世に出て20年以上経ちますが、出版当時すでにサンショウウオが激減傾向にあったこと、そして、現在も事態は悪化の一途をたどっていること。──今一度、サンショウウオを取り巻く現状を再認識し、保護のあり方を考える上でも、この本は貴重な資料となります。
絶版になった書籍を投票によって復刊させる復刊ドットコムをご存知でしょうか。
このサイトで100票以上集めると、復刊交渉の権利を得ることができます。(投票するにはユーザー登録(無料)が必要ですが、一度登録してしまえば、読みたいけどもう手に入らないアノ本この本に、どしどし投票することができるようになります。)
当サイトでは、上記の本の復刊を目指しています。
 をクリックし、あなたの一票をお願いします!!! をクリックし、あなたの一票をお願いします!!!
|
トップページ > サンショウウオとは > サンショウウオのための森林作り
|