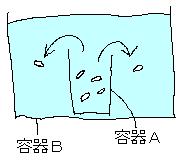2003年6月
2003. 6. 3 ポリプテルスにスジエビ与える
2003. 6.24 ワニガメのドライ濾過順調
2003. 6.25 喜びの報告
2003. 6.30 DX-3000G
ポリプテルスたちの最近の状況からお知らせします。
スジエビを発見
|
先日、スジエビが大量に繁殖している広〜いコンクリートのため池を発見してしまいました(らっちー!)。
水中の壁面にたくさんくっついていましたが、水中をホバリングしているものもうじゃうじゃいました。ヤマトヌマエビやビーシュリンプでは、泳いで移動することはあってもホバリングは見たことがなかったです。おもしろい。
|

スジエビ
|
活餌に採用
スジエビはポリプテルスの良い活餌になります。自家採取の活餌は病気を持ち込むデメリットがありますが、頑健なポリプテルスはものともしないはず(唯一怖いのは寄生虫マクロギロダクチルス・ポリプテリィ。これはポリ特有の寄生虫だからその辺にはいない。近所のショップのポリ水槽には蔓延してる(爆))。
さっそく30〜40匹ほど捕獲しました(予想以上に逃げるのが上手で苦労した)。
餌と割り切って、水あわせをせずにポリの水槽に放り込みました。
水質の変化に弱いエビの仲間ですから、悪くすれば数時間以内に全滅という可能性も頭をよぎりましたが、導入から10日以上経った今も、めちゃくちゃ元気にしてます。試しに水質がより悪いワニガメ水槽にも数匹放り込んでみたのですが(←鬼)、こっちもピンピンして、ワニガメの脱皮片など食べています。地元産だけに水が合うのかも。
ただし、餌としてどうかというと、スジエビは捕食されそうになったときバツグンの反射神経で逃げるので、ポリもなかなか手こずっているようではあります。ある意味、人工飼料ばかりで弛みきっていたポリ達には良い刺激です。
水槽への入れ方
池でスジエビを捕まえる際、水中の壁面をこそげ取るようにして網を振るったため、スジエビと一緒に、コケの塊や水垢なども大量に持ち帰ってしまいました。スジエビをポリプテルスの水槽に移すとき一番困ったのは、これらの”余計なもの”とスジエビを、どうやって分離するか、ということでした。
今回は結局、「・・・どりゃあぁああ!!」と、まとめて水槽に入れてしまったのですが、入れた後で良い方法を思いつきました。次回はこの方法を試したいと思います。
-
エビと”余計なもの”が入った容器Aを、水を張った大きい容器Bに沈める。
-
エビが泳ぎだすのを待つ(餌でおびき出すのも良い)。
-
全部泳ぎだしたら容器Aを取り出す。
-
容器Bのスジエビを一網打尽にしてポリの水槽に移す。
|
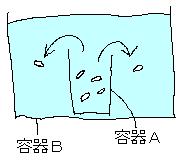 |
ドライタワー設置の様子について、「メッシュハンガーでドライタワー設置」と題してアクアリウムひと工夫のコーナーに掲載しましたので、ご覧になってみてください。
濾過機能の立ち上がりについて
ドライタワー設置後5日目頃から、緩やかな、しかし確実なpH低下が認められるようになりました。給餌後の水の白濁がほとんど見られなくなってきたのもこの頃から。濾材に目詰まりが生じないせいで、水換え翌日のpH急転直下はなし。スジエビも相変わらずピンピンしています。
順調すぎる(゚∀゚)!
・・・濾過のほうは順調なのだが、ワニガメがまたフンをしなくなった。
水温は高めにして頻繁に水換えしてるのに、なんで? ( iдi )アウウ・・・。
|
ウトウトしながら布団にもぐりこんだ時、ふと、ワニガメ水槽の水が妙に濁っていることに気が付きました。
放っておくわけにも行かず、しぶしぶ起き上がって中を覗いてみれば、そこには黄金が輝いていたのです!
☆*。・゜( ̄∇ ̄)。゜*。・☆
ピンセットで取り出して重さを測ってみると、約24グラムでした。
|

なんだかんだで、またもや約1ヶ月ぶりの排泄。
飼い方に問題があるのか・・・!?
|

世話になったのぅ・・・
|
私の不注意で3度も水に落とされながら、その都度奇跡の復活を遂げてきた愛機、カシオQV-2300UXが、先月末唐突に引退の時を迎えました。スイッチを入れてもエラーが出て電源が切れるようになってしまったのです。少しずつ内部の腐食が進んでいたのかもしれない。さらば。(;;)
|
新しいデジカメ
私にとって、新しいデジカメに必須の機能とは、
-
マクロ撮影の性能に優れていること。
-
水に落としても平気なこと。
の2点です。
検討の結果、デジカメはリコーのCaplio G3に決定。(実はすでに今月頭に購入して、もう使っています。)
【リコー Caplio G3 主なデータ】
- 324万画素
- 1cmマクロ
- レリーズタイムラグ0.14秒
(シャッターボタンを押してから、シャッターが切れるまでの時間)
使用した感想:画素数、マクロ性能にはおおむね満足。世界最速を誇るレリーズタイムラグであるが、暗いところ(フラッシュが必要な場面)では残念ながら性能が発揮されない。また、デジカメに共通の課題であるが、暗いとピントが甘くなったり、フラッシュをたくと極端な露出アンダーで真っ暗に写ることがあるなど、不満もある。(ファームウェアのアップデートに期待したい。)
とはいえ、現時点では総合的に判断して、小さな生き物の撮影にはこれがベストであろう。絶対買うべきだ。(リコー、なんかくれ。)
|
ヒミツ兵器
|
そして、先日ようやく、発売前に先行予約していたDX-3000Gが届きました(゚∀゚)!!。
DX-3000Gは、Caplio G3を水中で使えるようにするための専用のケースで、耐圧水深は55メートル。贅沢すぎる・・・うっとり。
|

ぐれいと!
|
さっそく、水槽の中に突っ込んで撮影してみました。
 
水の上からだと、なかなかこうは撮れない。
この夏は、海に川に大活躍する予定です!!!
そして、案外早く飽きる予定です(爆)。
トップページ > 出来事メモ > 2003年6月
|