2001年2月2001. 2. 3 確かにお腹が大きい2001. 2. 4 泳ぎの練習 2001. 2.12 マリンピア日本海 2001. 2.14 生殖結節 2001. 2.16 不安なこと 2001. 2.22 水中のクロサンショウウオ 2001. 2. 3 確かにお腹が大きい前回の初めての繁殖チャレンジは大失敗、結局1匹に怪我まで負わせてしまうというしまつ。観察も配慮も工夫も、全然足りませんでした・・・。懲りずに再度チャレンジです。 2度目の繁殖チャレンジ開始!本日餌を与えているときに、今までに見たことがないほどお腹がプリプリにはっている子がいるのに気が付きました。これはもしかして卵をもっているのか!?
|
| ところが、残念ながらお目当てのクロサンショウウオはコケに体を隠していて・・・。しばらく水槽の前で粘ったものの、結局体を見ることはできなかったのです。残念! トウホクサンショウウオの産卵もまだのようでした。日を改めてまた来ないと。近くていいけど入館料1,500円が痛いなあ・・・。 |  |
2001. 2.14 生殖結節
いくらメスが卵を持ったって、オスのほうも繁殖期に入らなければ受精は成功しません。その目安となるのが、総排出口の前端にある生殖結節(せいしょくけっせつ)と呼ばれる小さな突起の発達具合です。トウホクサンショウウオの水槽内繁殖の事例では、初めにメスのお腹から卵が透けて見え、後になってオスの生殖結節の発達が確認され、そこで水位を上げたところ産卵が行われたそうです。
| 写真がうまく撮れなかったのでへたな絵でスミマセンが、実は我が家のオスの中には、総排出口がこんなふうになっているものがいます。これが生殖結節なの? だとすると、後はメスのお腹の卵が発達すれば繁殖の準備が整うことになりますね! | 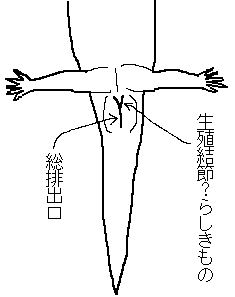 |
2001. 2.16 不安なこと
数日前に水面に油膜が発生。
アクアテラリウムにして水槽環境が変化したことで、濾過に何らかの影響があり水質が悪化したのかもしれません。そこでバクテリアへ豊富な酸素供給し濾過能力をアップさせるため、すぐ翌日に底床内に給水していた配管の一部をはずし、給水が水面にバシャバシャと落ちるようにしました。
しかし、後になってクロサンショウウオのオスが産卵時に波立て行動をして求愛することを思い出しました。こんなに水がバシャバシャいうような環境では、波立て行動をしても意味がないではありませんか!
そこで一昨日、給水パイプを延長して水面に近づけ、水面があまり揺れないようにしました。これだと酸素の供給量は落ちますが、実際に自然界でも春が近づき水温が上がると溶存酸素が低下し水質が悪化してくるので、逆に、産卵の季節を知らせる良い刺激になるかもしれない(ホントか!?(^^;)。
雌雄の判定が・・・
徐々に産卵に向けて環境面が整ってきている・・・。ただ、不安なことは、例の1匹は相変わらずお腹は大きいのですが、実はオスかもしれないということです。
クロサンショウウオはオスのほうが大きくなりますが、その子は8匹の中で最も大きいのですよ。やっぱり単なる太ったオスなのかな・・・。私は相変わらず、知識・観察力ともに低レベルだ・・・。「はふ。ちょっとため息。」
※本日よりHPに公開。ここはやっぱり皆さんのご意見を伺い、ご指導を仰ぐのがよいかと・・・(^^;。
2001. 2.22 水中のクロサンショウウオ
| 特に産卵の兆しはありません。目下、水槽の1/3以上を水没させ、深いところで10cm程度の水深としていますが、ほとんどの個体は陸地に設置してある流木の下に隠れています。しかし、水中も嫌いというわけではなく、水槽を見るとたいてい1匹は水中にいるのが観察できます。 餌に対する反応クロサンショウウオは、じっと餌の昆虫などが目の前を通りかかるのを待ち、目の前に来た瞬間に食べるのが普通で、動かない餌には見向きもしないのですが、中には水中にばら撒くだけで餌を食べる個体もいるそうです。 |  |
私はいつもピンセットで餌を与えていますが、確かに水中のクロサンショウウオは陸上で与えるよりも興奮した感じになり、積極的に餌に向かってきます。例えば、3〜4cm離れた位置の底砂をピンセットで突付くだけで、明らかに餌を探している素振りをみせ、水底を蹴って追いかけてくるのです。
陸上でも、数センチ前方でミミズが跳ねまわるような派手なアクションをすると、食欲を刺激されるのか自分から近づいていって食べますが、水中では、昆虫を近くに落とすだけで寄ってくる(今のところ寄ってくるだけで食いつきませんが)など、反応が非常に顕著。水中のほうが軽やかに動けるということもひとつの要因だと思いますが、それだけでは説明できない何かがある!
基本的には待ち伏せ方の捕食者とはいえ、これなら我が家でも慣らせば水中に肉片や人工飼料をばら撒くだけで食べるようになると思いました。食べ残しで水を汚したくないので、私は今後もピンセット派ですが。
誤食の心配
さて、上記のような性質がわかって、底砂として使っているハイドロボールの誤食が心配になりました。こちらに書いたとおり、私が底砂にハイドロボールを選んだ理由の一つは”粒が大きくて誤食されにくい”ということでしたが、実際には、ハイドロボールの中にはクロサンショウウオの口に入るほど粒の小さいものも混ざっていました。しかもハイドロボールは比重が軽く、浮きやすい。もしも、その浮いたハイドロボールが濾過器の水流に乗って、クロサンショウウオの目の前で動いたら・・・。あるいは、水中のクロサンショウウオが動いた拍子に粒の小さいハイドロボールが巻き上がったら・・・。思わず「ぱくっ」とやってしまう可能性は否定できません。
夢に見たんです(^^;
実は先日、クロサンショウウオがハイドロボールに食いついてすぐに吐き出すという夢を見て(実話)、急にこのことが心配になったわけ(^^;。私も参加させてもらっているAMPHIBIAN Mailing Listで、大型になる有尾類がハイドロボールを飲み込んで死んでしまったという例を教えていただき、そのことも心のどこかで気になっていたのかも(このメーリングリストには両生類に詳しい方がたくさん参加していて、とても勉強になります)。
早いところ、元の水深0に戻したいです。
| ←前のページへ | | 次のページへ→ |
トップページ > サンショウウオ観察レポート > 2001年2月
 | URL : http://xto.be/ | ご質問等ありましたら掲示板にお願いします。 ※完全リンクフリーです。ご自由にどうぞ。 |

