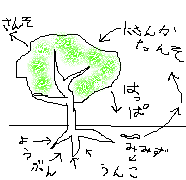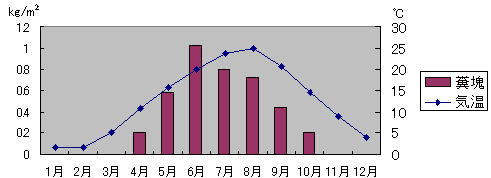2006年2月2006. 2. 7 給餌の極意を模索する(その1)2006. 2.12 給餌の極意を模索する(その2) 2006. 2.16 繁殖期がやってきた 2006. 2.25 給餌の極意を模索する(その3) 2006. 2. 7 給餌の極意を模索する(その1)相変わらず、ちびくろ(♂)の食欲が旺盛すぎる。餌をねだってくるのは元気な証拠だと思いますが、食欲に任せて食べさせることが健康に良いとは思えません。 んで、より適切な給餌を検討するため、昨年末から「土壌動物のバイオマスの季節変動」についてちょびちょびと調べてきたわけですが、この辺で中間報告しときます。
土壌動物の個体数の季節変動下は、上記文献の北海道の天然林の土壌動物データの中から、サンショウウオ成体が好んで食べていると思われる種類を抜き出し、季節ごとの個体数の移り変わりをグラフにしたものです(1m2当りA層以上)。 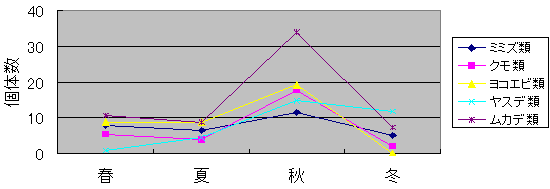
どの種類も秋に最も多いことが分かります。そして、夏に最も少ないです(ヤスデ類を除く)。房総半島での調査でも夏季にワラジムシ目の減少が確認されており、ヒメミミズのデータでも8月と10月に少なくなっています。 春から夏にかけての減少はいまいち釈然としませんが、秋にドンと増えるのは、きっと落ち葉が増えるからです。土壌動物の多くは落葉落枝などを食べる分解者ですから、進化の歴史の中で、食べ物の多い季節に個体数が多くなるようなライフサイクルが確立されたのだろうと思います。そして、それら分解者の個体数が多くなる秋は、それを狙う肉食の土壌動物にとっても個体数が多くなってしかるべき季節でしょう。 季節ごとの給餌頻度の手がかりさて、先のグラフより、季節ごとの土壌動物の生息密度はおおよそ「春:夏:秋:冬=1:1:2:1」と分かります。この比例関係に、サンショウウオが待ち伏せ型の捕食者であることを考慮して土壌動物の行動量係数(活発に行動する季節ほど値が大きい)を乗じることで、捕食チャンス(獲物との遭遇確率)の季節変動が割り出せます。これを手がかりに、季節ごとのより適切な給餌頻度を定めようという考えです。 サンショウウオが捕食する土壌動物はすべて外温動物なので、その行動量は地温の関数である程度表せるかもしれません(もしそうなら水槽内の水温を代入しての検討もできる)。まずは、その辺に関する文献をあたっていきたいと思います。 2006. 2.12 給餌の極意を模索する(その2) というわけで、餌となる土壌動物の行動量と地温との関係について調べているところですが、その第一歩が下のグラフ。 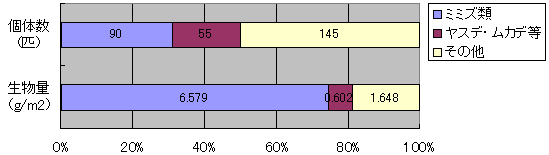
生物量はミミズがぶっちぎりトップで、全体の74%を占めています。したがって、ミミズの行動量と地温との関係さえ調べれば、全体の傾向を7割以上の精度で推定できるということになります!と、いうのは詭弁ですが(笑)、餌として重要なのは個体数よりも生物量の大小なので、ミミズで代表させるのは妥当だろうとの判断です。いちおう下記文献以外にも何冊かの専門書(小学校低学年向け「みみずのかいかた」など)をあたりましたが、たいていの森林土壌では(程度に差はあるが)ミミズの生物量が多い傾向があるみたいです(ただし、森林より草地のほうがさらに多いという)。
次回、「その3」では本題に入ります。ミミズは人気者なのですぐに調べがつくと思いきや、意外とてこずってます・・・。 2006. 2.15 繁殖期がやってきた 豪雪だったこの冬もぼとぼち終わりそうです。雪解けが進み、背の高さを超えてそそり立っていた道路脇の雪の壁もずいぶんと低くなりました。そんなこんなで、今年も繁殖シーズン到来。
すでに報告のとおり、出だしの越冬スポットの試みからして不成功。半数以上の個体がはなから水に入って越冬するしまつ。(ノ∀`)アチャー 降雨の表現方法もはや意義は薄いですが、せっかくだし、計画はこのまま続行することに。
今後しばらく、実際の雨天の日にあわせて水槽内にも”雨”を降らせてみます。 メモ昨日、陸地には3匹[デ(♂)、刃(♂)、お(♀)]。アカミミズを給餌し、水中の2匹が食べた[ch(♀)、ち(♂)]。水温は9℃。ちなみに1月29日はビックリ3℃だった(今シーズンの最低水温)。 2006. 2.25 給餌の極意を模索する(その3)
ミミズの行動量と地温 さて本題。その2において、餌となる土壌動物のふるまいをモデル化するためミミズの行動量と地温との関係をみることにしました。はじめに調べたのはミミズの呼吸量に関する研究報告。温度が高くなると呼吸量が増えることが分かりましたが、呼吸量が増えると行動量も増えるかどうかは、よく分かりませんでした。そこで、次に目をつけたのがミミズの”糞塊”です。
|
| ←前のページへ |
|
次のページへ→ |
トップページ > サンショウウオ観察レポート > 2006年2月
 |
URL : http://xto.be/ | ご質問等ありましたら掲示板にお願いします。 ※完全リンクフリーです。ご自由にどうぞ。 |