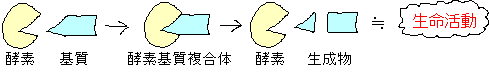2005年2月2005. 2. 6 冬眠か越冬か2005. 2.11 水位アップ 2005. 2.17 水位アップのその後 2005. 2.22 水生型への変化 2005. 2.28 トウキョウサンショウウオ・シンポジウム 2005. 2. 6 冬眠か越冬か「冬眠」という言葉には、土に潜り仮死状態で冬を越す、というイメージがあります。両生類誌上でも、死んでしまったと勘違いされ、危うく埋葬されそうになった冬眠アマガエル「ますじろう」のエピソードがありました(佐藤千尋さんのカエルエッセイはとても面白い)。 私は冬眠中の事故死が怖いため、今年も冬眠しない程度の温度でサンショウウオを飼育していますが、具体的には、肺呼吸を行っていれば仮死状態ではない=冬眠していないという判断です。
サンショウウオは仮死状態になるのか?サンショウウオもカエルも同じ変温動物。体温が下がると動きが鈍くなる理屈も同じだろうと思います(下図参照)。
|
|
生ミズゴケの養生は、十分に湿らせた後ビニール袋に入れ、日のあたるカーテンレールの端に吊り下げて行ってます。生命力を感じさせる黄緑色になっており、意外に順調か? |
 |
2005. 2.11 水位アップ
メモ
- 2月7日
-
5日のメモに大事なことを書き忘れ。ちびくろ(♂)は、ミズゴケから掘り起こされた直後の摂餌だった。
- 2月9日
-
雨降り。日中の水槽温度は10℃に達した。早春(晩冬)の雨が野生のサンショウウオの産卵の契機になることを考えると、方針より少し早いが、ミズゴケを撤去し水場設置に踏み切るべきタイミングかも!?
- 2月10日
-
日中は雨→夕方から雪がちらつく。水槽温度は8℃。天気予報ではこの先も雪だるまマークが続いているが、積もるより融けるほうが早い季節(サンショウウオの産卵シーズン)に入った印象強し。・・・よし、やるか。
やりました
|
思い立てば早い。水槽左側に埋めてある”かめ”からミズゴケを撤去し(中には4匹が潜んでいた)、代わりに水で満たしました。さらに注水して、底床の2/3程度を水没させました。 |
|
・・・ただ、このように準備万端整えた”産卵用のかめ”よりも、水槽右側の緩傾斜地にできた水場のほうがずっと広くて居心地よさそうなのは誤算でした(爆)。
水中の様子
|
水位は1分程度の間に一気にアップさせましたが、パニック状態に陥るなどの問題は起きず一安心。水を注いだ直後には、左写真のとおり水槽の片隅に固まっており、しばらくすると方々に散っていきました。 この”かめ”は、やはり小さすぎ。壷型の構造にも問題があります(泳ぎの下手なキョロチビがうまく上陸できない様子が認められた)。とりあえず、大き目の流木を突っ込んで脱出経路を作っておきましたが、どうも不安であり、大幅な改善の必要性を感じています。なお、産卵床として、後ほど小枝を用意する予定。 |
毎度、当たらない宝くじを買うような気持ちで水位アップを行っていますが、産卵しなかった場合には、宝くじと違って運のせいにできないのが辛いところ・・・。
メモ(続き)
- 2月11日
-
水位アップから一夜明けた今朝、外は見事な銀世界。夜中降り続けたらしい。水温は7℃まで低下。えっと、早まったか・・・な?
なお、昨年10月頃から6時間に短縮していた照明時間を、昨晩より元の8時間に延長(本当はもっと前から少しずつ伸ばしていくつもりだったが、すっかり忘れていた)。
2005. 2.17 水位アップのその後
10日夜〜15日夜までの丸5日間に渡り、以下のとおり水場を設けて飼育しました。
| 前半2日間 | 約30%の陸地を残して水没 |
| 後半3日間 | さらに水を足して100%水没 |
ただし、後半まったく陸地を作らないことには不安があったため、流木を積み重ねて”島”を作っておきました。その結果、
-
キョロチビは”島”の上に避難し、5日間いっさい水中に入らなかった。
-
残りの9匹は水中の流木の下に隠れるなどして、5日間のほとんどを水中生活。
|
右写真は、水中にいるゆきどけ(♀)の下腹部です。総排出口の周囲がぽっこりと膨らんでいることが印象的。陸上ではメスはぺったんこな印象があるので、多少は季節的な性徴が出ているのかもしれませんが、単なる浮力の影響にも思えます。 |
|
オス個体の体型変化も特に見られなかったので、15日に一旦水を抜き、元の陸地に戻しました(ただし、”かめ”には方針どおり引き続き水を湛えています)。
今後の予定
繁殖期に水に入っても、何らかの原因で水生型への生理的変化が起こらなかった個体は、変化が起こるまで水中を出たり入ったりするそうです(「彷徨行動」)。
そこで、昨年同様、雨天の日を見計らって湛水し、数日後に元に戻すという方法をしばらくの間続けてみようと思います。このような方法で「彷徨行動」と同様の結果が得られるかは私にはわかりませんが、淡い期待感はあり。
本日は雨天なので、早速、2回目の水位アップを行う予定。今度はすでに水に慣れているので、初めから100%水没させます(水に入ろうとしないキョロチビは隔離ケースに避難)。
メモ
- 2月12日
-
”かめ”に替わるより良い”産卵ケース”について鋭意検討中。上向きのまま水面ギリギリまで沈めることができる容器は、大雑把に言って、その容器に目いっぱい汲んだ水の重さと同じくらいの重量が必要(物体を水に入れると、押しのけた水の重さと同じだけの浮力が働く)。そんなに重い容器など売っていない。よーし、純金(比重19.3)で自作しよう。
むなしい妄想はさておき、釣具屋に行って釣り用のオモリを見てきた。両手ですくった位の量で約3キロ。鉛の毒性の問題を何かに密閉して用いることでクリアすれば利用可能か!? - 2月14日
-
まだ生んでない。もはやタイムリミット。明日の朝に望みをかける!
- 2月15日
-
水を抜いて通常飼育に戻した。
水を抜いた直後はちょっと落ち着かない様子で動き回っていた。水の中が意外に快適だったのか?とりあえず、健康を害している様子はなく一安心。 - 2月16日
-
昨日水を抜いた時には”かめ”の水には1匹も入っていなかったが、今日見ると4匹が入っていた。自ら水中を選んだ。内訳はオス2匹、メス1匹、性別不明1匹[デ、ち、わ、サ]。すべてオスなら意味のありそうな現象だったのだが。う〜む。
ちなみに、”かめ”には上陸しやすいようでっかい流木を突っ込んであるため、産卵スペースはほとんどない。なるべく早く新しい容器(もっと上陸しやすい形のもの)に取り替えたい。
冷凍アカムシを給餌し、2匹が食べた[は、キ]。
2005. 2.22 水生型への変化
2回目の水中飼育は、17日夜〜21日朝までの丸3日半続けました。今回も水を抜くと落ち着きなく動き回る様子が観察できましたが、中には底床に頭を突っ込んだままピクりともしない者もあって(指でつついたら慌てて動き出したが)、非常に心臓に悪い。
相変わらず産卵はなく、正直、このように強制的に水の中ですごさせる方法が本当に正しいのか?単なる虐待なのでは?と不安が募ります・・・。
ところが
よく見れば、数匹の尾がなんとな〜くヒレ状化。最もそれが顕著なちびくろを撮影し、比較してみました。写真【上】が約1ヶ月前の姿、写真【下】が今回水を抜いた直後の姿です。

先月19日の様子。尾の先端部のみヒレ状になっている。

2月21日の様子。尾が根元のほうまでヒレ状になり、首筋も太くなっている。
確かに変化してる!(*゚∀゚)=3
こうなると、今度は一転、水を抜いたことが虐待に思えてきました( ̄▽ ̄;。まったく変化のない個体もあるので、とりあえず少しだけ水を足し戻し、一部に水深0〜3cm程度の浅い水場を設けておきました。
10匹もいるのですから個体ごとの水生適応時期に差が出て当たり前。しかし、私にはそこまでの想像力が足りなかった!やはり自由に出入りできる十分に広い水場か、あるいは水生化した個体を引き続き水中飼育するための専用ケースが必要です。
何はともあれ、一歩前進だ!
メモ
- 2月18日
-
水位アップ翌日。昨晩水位を上げた際に”島”に避難した個体は入水していた。産卵の兆しはなし。計画的な繁殖のなんと難しいことか・・・。
- 2月19日
-
トウキョウサンショウウオ研究会主催の第7回トウキョウサンショウウオ・シンポジウムに出席。
- 2月21日
-
水を抜いた。夜ミミズを給餌し、6匹が食べた[デ、ゆ、刃、お、ね、ち]。サンボは一度噛み付いたが吐き出した。水生期間中は餌を食べないと聞いたことがあるが、なぜか皆食欲旺盛。なお、尾のヒレ状化はオスだけでなくメスにも見られる。
2005. 2.28 トウキョウサンショウウオ・シンポジウム
現在、東京都で絶滅の危機に瀕しているトウキョウサンショウウオは、かつては都内の美しい里山を象徴する生き物だったそうです。
トウキョウサンショウウオのことをもっとよく知り、人と自然とのより良い関係づくりを考える場として、毎年このシンポジウムが開催されています(主催のトウキョウサンショウウオ研究会の皆さんのご尽力に敬意!)。
|
7回目の開催に、私は念願の初参加。 |
|
報告及び講演は、トウキョウサンショウウオ他ヒダサンショウウオ、アカハライモリに関する5題目。中でも『トウキョウサンショウウオは三面コンクリート水路で繁殖できるか?』という埼玉県立松山高等学校生物部の皆さんの講演がおもしろかった!まだ研究者の卵ということで科学的な論法は不十分ながら、「今、サンショウウオのために何ができるのか」大きなヒントをもらいました。
この件については考えを整理し、おって報告したいと思います。
メモ
- 2月23日
-
午前中は雨。午後から晴れた。迷ったが、夜に水位アップ敢行。ところが、直後から次々と”島”に避難!空中湿度が低くて水に入りたがらなかったのか!??
なお、キョロチビとねじ巻きの2匹は、あらかじめ隔離ケースに退避。
- 2月24日
-
ねじ巻きが隔離ケースから脱走し、本水槽の水に浮かんでいた(隔離ケースは本水槽の中に置いてある)。特に問題なさそうだったので、そのままにしておいた。
- 2月25日
-
おぼろ月(♀)が、隔離ケース内に侵入していた。特に問題なさそうだったので、そのままにしておいた。
- 2月26日
-
水を抜いて陸上飼育に戻した。ただし、1/2ほどは浅い水場として残した。シェルターとして流木を2本追加。また、湿度計を購入して設置。
- 2月27日
-
今年も繁殖は失敗に終わる予感。昨年の震災で我が家のクロサンショウウオの個体群生息地も大ダメージを負った。だから今年こそは自家繁殖した個体を還元したいという、密かな想いがあったのだが・・・。気分転換に、いわゆる「松田優作4コマ」を作ってみた。
| ←前のページへ |
|
次のページへ→ |
トップページ > サンショウウオ観察レポート > 2005年2月
 |
URL : http://xto.be/ | ご質問等ありましたら掲示板にお願いします。 ※完全リンクフリーです。ご自由にどうぞ。 |